『ナスを育てたいがどれを育てたらいいかわからない。』
種売り場を覗いたらたくさんの種があり、困ってしまった。
そんな経験ありませんか?
ナスは世界中で1000以上の種類があるといわれます。
今回はナスの種類や栄養など基本的な情報について解説します。
これから、家庭菜園を始める方、ナスの栄養や食べ方、美味しいナスの見分け方を知りたい方向けの内容です。
- ナスの品種と在来種
- ナスの栄養
- ナスの保管方法
- ナスの目利き
ナスの種類

ナスはナス科ナス族の一年生植物で原産はインドになります。
日本に伝わったのは奈良時代、当時は「なすび」と呼ばれていたようです。
旬の時期は6~9月。
主な産地は、夏秋ナスは群馬県、茨城県、栃木県が盛んで、シーズン外のスーパーで並ぶナスは、高知県、熊本県、福岡県産が主になります。
ナスの代表的な品種

代表的な品種ってどんなものがある?



特徴と用途も交えて解説するね。
日本だけでも200品種程あるといわれます。
ナスは形や大きさによって、丸ナス、長ナス、中長ナス、大長ナス、米ナス、小丸ナスに分類され、色によっても緑、白、赤、縦じまと種類は豊富です。
種類について紹介していきます。
| 品種名 | 形状・サイズ | 特徴 | 向いている料理 |
|---|---|---|---|
  千両ナス | 中長型(約12〜15cm) | 日本で最もポピュラー/ 皮が柔らかく扱いやすい | 焼きナス 煮物 炒め物 漬物など万能 |
  長ナス | 細長型(約20〜25cm) | 肉質が柔らかく、 焼きナスに最適 地域ごとに固有種あり | 焼きナス 揚げ浸し グラタン |
  大長ナス | 超長型(約40〜60cm) | 九州地方で多く栽培/ 皮はやや硬め、果肉は柔らかい | 焼きナス 田楽 麻婆茄子 |
  丸ナス | 丸型(野球ボール状) | 肉質がしっかり/ 煮崩れしにくい/ 伝統野菜が多い | 煮物、田楽 ステーキ風 |
  小ナス | 小型(約8cm/10〜20g) | 漬物に最適/ 見た目がかわいらしい | 浅漬け からし漬け 炒め物 |
  米ナス | 大型・丸型 | アメリカ原種/ 皮が硬く果肉が締まっている | ラタトゥイユ ステーキ 田楽 |
  泉州水ナス | 丸型・やや小ぶり | 水分が非常に多く、 生食も可能/ 大阪の特産 | 浅漬け サラダ 生食 |
ナスを使ってどんな料理を作っていくかで選ぶ品種も変わりますね。
基本は焼くにも対応する万能型の千両ナスがポピュラーですよね。
スーパーでよく見かけるのもこの形。
珍しもので種を選ぶのも良いですよね。
選び方は人それぞれです。
では地域特有の在来種はどうでしょう?
地域の特産・伝統品種(一部)
加茂ナス
加茂ナスは京都を代表する伝統野菜であり、味・形・文化的背景のすべてにおいて特別な存在です。
京都市北区上賀茂が発祥の地で、上賀茂神社との深い関係があり、初収穫の加茂ナスは神社に奉納される。
丸ナスの一種で直径10~15㎝位で重さもそこそこあり、300~500g。
濃い紫色で光沢がありヘタの下が白いのが特徴で、果肉が緻密で煮崩れしにくく、加熱するととろけるような食感で味噌田楽、揚げ出し、煮物、丸焼き、しば漬けがおすすめの食べ方。
露地栽培が中心で、6~8月中旬ころが収穫ピーク。
泉州水ナス
州水ナスは、大阪府南部・泉州地域(岸和田市、貝塚市、泉佐野市など)で栽培される、日本でも珍しいほどみずみずしい伝統野菜です。
水分量が非常に多く、皮は非常に薄い。
独特な甘み、えぐみが少なく果肉が柔らかく、口当たりなめらか。
生食、漬物、生ハム巻き、じゃこごうこが定番の食べ方。
漬物は名産、じゃこごうこは郷土料理として愛されています。
ハウス栽培で3月下旬〜6月頃、露地栽培で5月〜8月が最盛期。
毎年5月20日は「水なすの日」としてイベントも開催しているようです。
ホームセンターで購入できる変わり種



紹介していないものでも面白いナスがたくさん。
ホームセンターでも販売しているのはこちら。
白ナス


白ナスは写真のとおり、皮が白いナスのこと。
普通のナスより皮が硬いですが、中身は水分量多めで加熱したらトロトロな食感になります。
別名、「トロナス」とも呼ばれます。
「とろ~り旨なす®」はトキタ種苗の商標で、白ナスのF1品種。
皮が柔らかく、果肉が緻密で加熱調理に最適で、揚げると「麻婆豆腐のようなとろみ」になると高評価。
天ぷら、唐揚げ、グリル、ディップなどにおすすめ。
庄屋大長


庄屋大長は果長35〜40cmにもなる超ロングサイズの大長ナスで、見た目のインパクトと味の良さから家庭菜園でも人気の高い品種です。
大長ナスの中でも大きいサイズです。
黒に近い濃紫色で、果肉は柔らかく、種が少なく、調理の際にはアク抜き不要。
皮が柔らかく、油との相性が抜群で焼きナスにすると絶品。
火が通りやすく、炒め物・天ぷらもおすすめ。
耐暑性が高く昨今の夏場の栽培にもおすすめ品種。
ナスの栄養と食べ方
栄養としては、下記のような栄養成分と作用があります。
- ビタミンK … 10㎍
- 葉酸 … 32㎍
- カリウム … 220㎎
- 食物繊維 … 2.2g
- 糖質 … 2.9g
ナスニン(アントシアニン)
- 抗酸化作用
- 生活習慣病予防
- 老化防止
ナスは漢方では体を冷やす野菜として、鎮痛や消炎の為に使われてきました。
『秋なすは嫁に食わすな』
ということわざは、体を冷やすことを心配する気遣いから生まれてとされる説も有力です。
色素成分のナスニン(アントシアニン)は皮に含まれ、コレステロールの酸化を防ぎ、老化やがん化を抑え糖尿病、高血圧などが気がかりな人向けの野菜です。
また、あく成分のクロロゲン酸も、抗酸化成分であるポリフェノールの一種。
活性酸素による過酸化脂質の生成を抑え、生活習慣病全般の予防と改善に効果をもつとされます。
食物繊維・カリウム は 腸内環境改善・むくみ予防の効果。



栄養を維持する調理方法は以下の通りです。
調理と食べ合わせ


ナスニン(アストシアニン)を含む皮は捨てずにしっかり食べるようにしましょう。
油と相性がよく、揚げることで甘みが増します。
給油率が高く、カロリー過多になりやすいため、熱湯をかけて油切りをすると余分な油脂をカットできます。
ナスは陰性野菜、温性食材と組合せとバランスが取れる。
例えばショウガやカボチャとの組み合わせが良い。
逆にソバとの組み合わせは体を冷やす原因になります。
おいしいナスの見分け方
おいしいナスの見分け方については下記、5つチェックしてみましょう。



せっかく購入するならおいしいナスを選びたいですよね。
色とツヤ


濃い紫色でツヤがあるものが新鮮です。
くすんだ色や色ムラは避ける。
理由は色々ありますが、ボケナス化、成熟がすすみ果実が茶色になり、味が落ちていきます。
形


ふっくらしていて均一な形。
細すぎたりいびつな形は成長不均一の可能性があります。
ヘタとトゲ


ヘタがピンと立っていて、トゲが鋭いものが新鮮。
しおれたヘタは鮮度が落ちている。
皮の質感


なめらかで弾力があるものが◎。
しわや傷があるものは避ける。
収穫・輸送時の擦れや打撲で、皮にかさぶたのような茶色い斑点ができることがあります。
食べても害はありませんが、見た目や食感に影響します。
重さ


持ったときにずっしりと重みがあるものを選びます。
ほかの野菜も同様ですが、水分が豊富でみずみずしく新鮮である証拠です。



ナスは3本セットで袋詰め販売と単体販売があります。
3本セットなら重さがわかりづらいですが、それ以外の視覚情報はわかります。
①~④を判断して購入していきましょう。
水気が大事で鮮度が重要な野菜です。
街の直売所などで販売されいてるものが新鮮です。
購入先も意識してみては如何でしょうか?
ナスの保管方法



ナスは野菜室で保管すればいい?



保管方法についてみてみましょう。
ナスの保管方法について常温、冷蔵庫、冷凍について簡単に説明します。
おすすめ 冷蔵保存
ナスは寒さに弱く、5℃以下で低温障害を起こすため、冷蔵庫の野菜室(7〜10℃)が最適です。
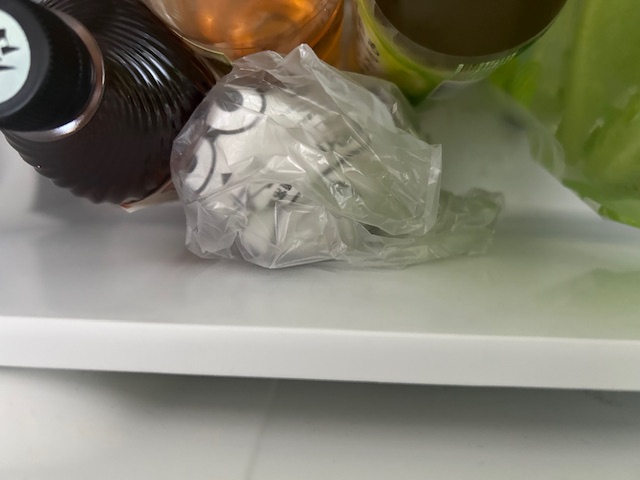
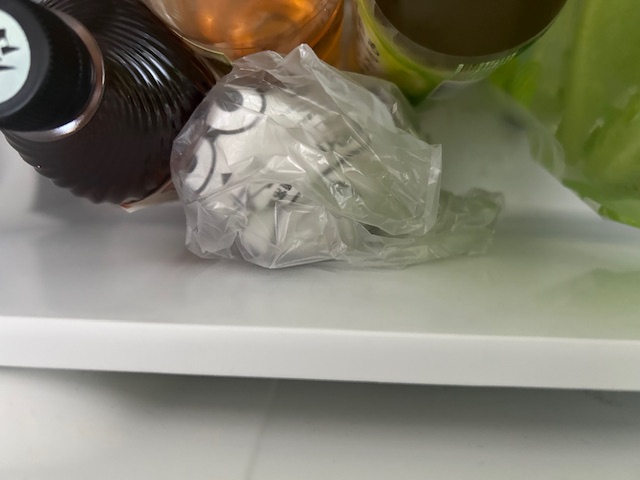
1本づつペーパータオルや新聞紙で包み、ビニール袋に入れて乾燥を防ぐようにしていきます。
ヘタを上にして立てると、収穫時の状態に近くなり長持ちする。
保存期間は約1週間。
しなびる前に使い切るのが理想です。
1本単位で使い切るようにしましょう。
半端になるようなら冷凍保存の方が適しています。
常温保存


春秋なら冷暗所のような場所で常温保存も可能です。
ただし、夏場は高温すぎるため不向きです。
湿らせた新聞紙で包み、ポリ袋に入れて乾燥を防ぐようにしていきます。
しなびやすいので、こまめに状態を確認しましょう。
春秋で、2~3日ほど保管が可能です。
野菜室保管の方が手間が少ないため、常温で保存するよりも、早めに食べきるようにしましょう。
冷凍保存


冷凍保存は2種類があります。
生のまま、加熱したものを冷凍する方法です。
生のまま冷凍する場合、ヘタを取り、輪切りや乱切りにして水分を拭き取り、保存袋に入れて冷凍します。
加熱して冷凍する場合、素揚げや炒めてから冷凍すると、とろとろ食感が楽しめます。



使用する時は?
自然解凍は水っぽくなるため、凍ったままでフライパンなどで加熱調理していきます。
保存期間は冷凍してから1ヶ月程度です。



保存は野菜室で保存していくのがベストです。
極力、新鮮なうちに食べてほしいですが、食べきれない場合は野菜室で乾燥を防止しながら1週間ほど保存していきます。
無理なく使い切れそうですよね。
ナス 目利きや保存方法 雑学 まとめ
今回はナスの品種、栄養、美味しさの見分け方、保存方法の基本的な情報についてお伝えしました。
少し、ボリュームが多かったかもしれません。
家庭菜園では毎年育てたい野菜ですが、品種が多く、これと決めて購入される方は一握りのような気がします。
育てたい品種の選考に一助となれば幸いです。
如何でしたでしょうか?
今回、以上。
最後までお付き合い頂きありがとうございました。
ナスの育て方についてはこちら


ナスのスピリチュアル的な話しについてはこちら
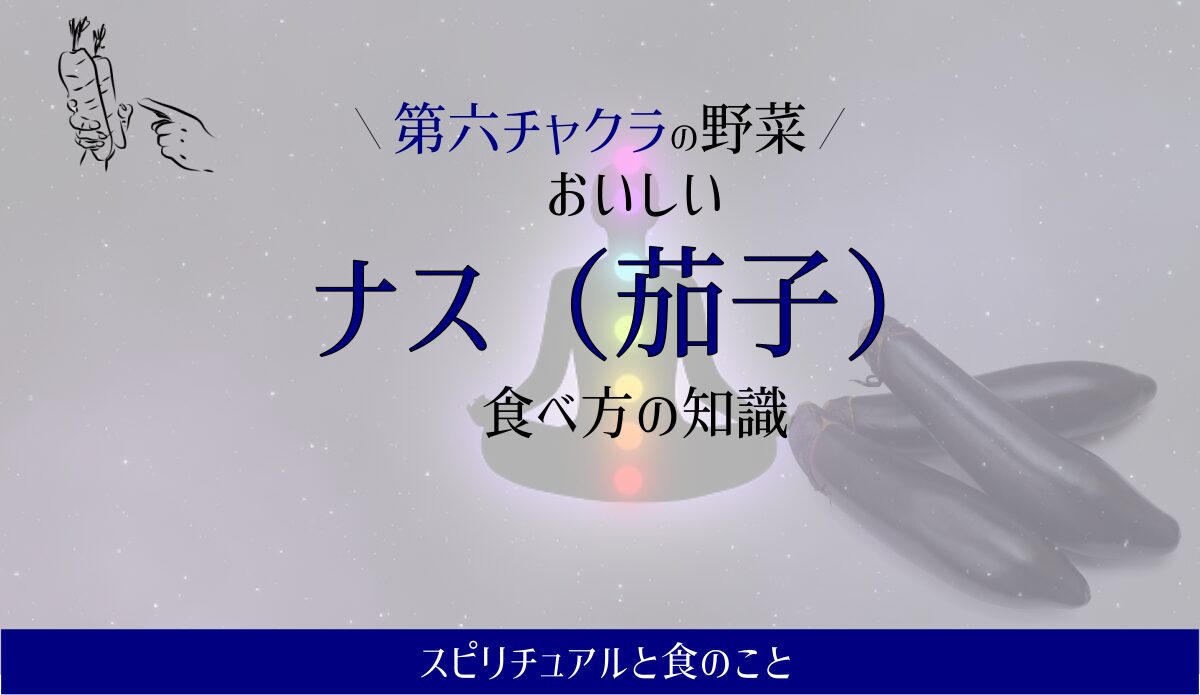
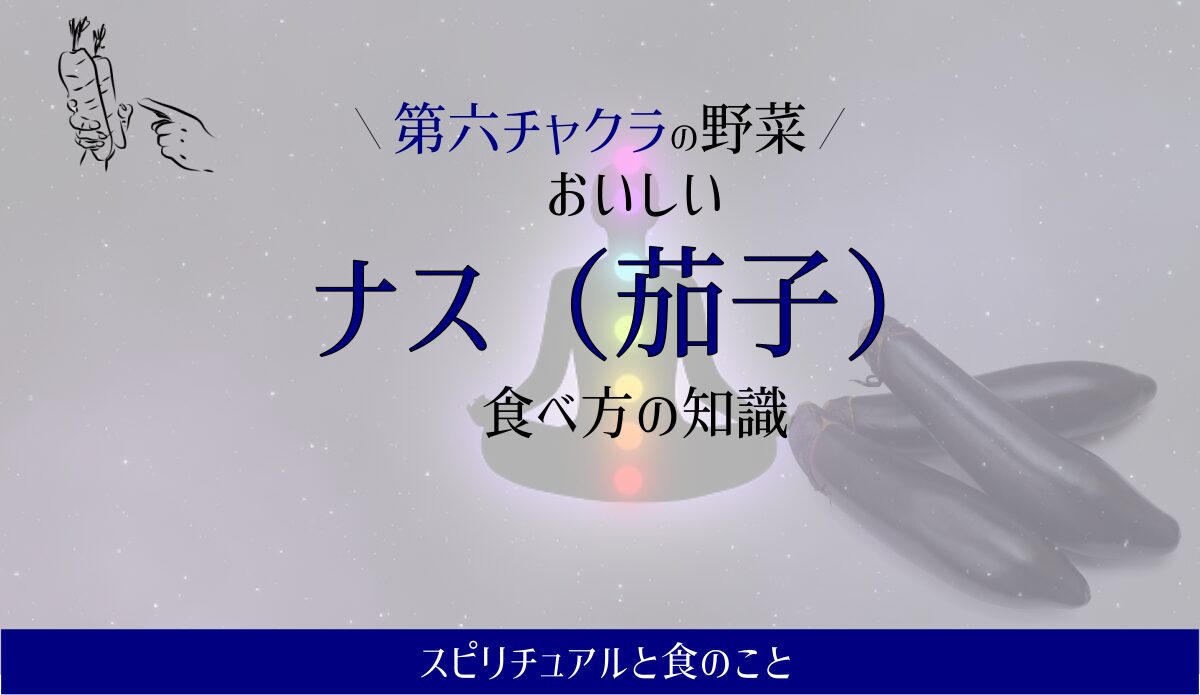

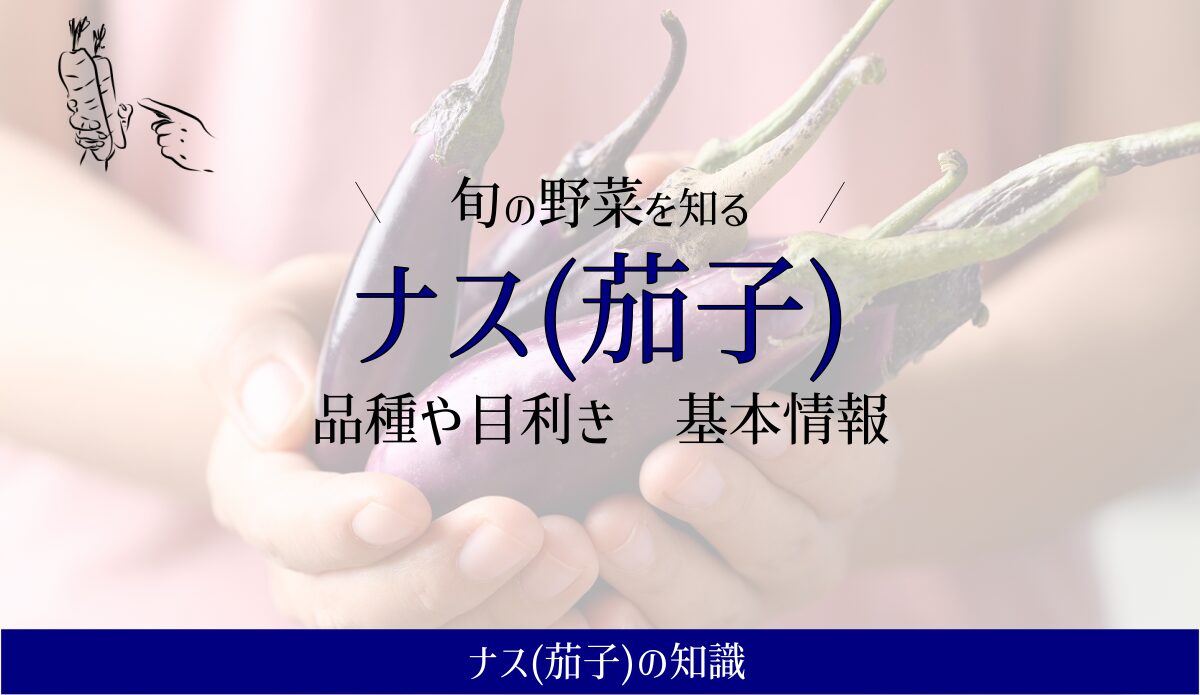





コメント