『花や野菜にシミがある』
こういう経験ありませんか?
これ、もしかしたらスリップスという1㎜くらいの小虫が実や花の中を徘徊していませんか?
今回はこのスリップス(アザミウマ)の対策について解説していきます。
スリップスの対策にお悩みの方、これからバラを育てたい方向けの内容です。
- スリップス(アザミウマ)について
- スリップス(アザミウマ)の予防と対策
スリップス(アザミウマ)とは?


スリップスの特徴についてみていきます。
そもそもスリップスって?


肉眼で見るとこのくらいのサイズになります。
アザミウマ、別名をスリップスといいいます。
和名「アザミウマ」は、昔の子供遊びでアザミの花を振って虫を出すことから名付けられたそうです。
体長1㎜前後と非常に小さく、高温乾燥期や農薬使用の多い場所に多発します。
幼虫と成虫が新芽、葉、花、果実などの柔らかい部分を集団で吸汁し加害していきます。
種類によっては数種のウイルス病を媒介します。
葉裏に卵を植付け、幼虫から蛹になり成虫へとなりますが、高温時は繁殖が旺盛になり、1~2週間で成虫になります。
世界中に6000種以上おり、日本でも数百種ほどが存在しています。
スリップスの発生時期と原因
スリップスの発生時期は、気温が25℃の高温で乾燥している状態だと繁殖確変にはいる。
時期は4~10月の暖かい時期に発生しやすい。
条件がかみ合ってしまうと年10回以上の発生もありえます。



気温を20℃以上をキープするハウス栽培では、冬場でも発生する可能性があります。
ミカンキイロアザミウマ、一部の種は露地でも越冬します。
越冬する場合、周囲の雑草に潜み冬を超え、また暖かくなったら野菜や花についていきます。
飛翔能力は弱いですが、風にのって侵入していき、マルチの網の大きさが荒ければ意味がないのが難点です。
スリップスが発生しやすい野菜や花



スリップスが発生しやすい野菜は?
| 名 | 植物名 | 備考 |
|---|---|---|
| ネギ類 | ネギ、ニラ、ワケギ、アサツキ | ネギアザミウマが多発。 春〜初夏に注意 |
| ラッキョウ、タマネギ | 葉の付け根に潜みやすく、 吸汁痕が目立 | |
| 根菜類 | ニンニク | 葉の変色や奇形が起こることも |
| 葉菜類 | ホウレンソウ・シュンギク | ケロイド状の奇形葉が発生 |
| 果菜類 | スイカ・アスパラガス | 果皮にかすり傷、イボの退化など |
| ナス・ピーマン・キュウリ | ミナミキイロアザミウマによる 被害が多い |
花では、バラやカーネーション、キク、ペニチュア、パンジーなど。
花の中に入り込んで吸汁するため、花弁の変色や奇形が起こりやすく、観賞価値が下がってしまいます。
スリップスの被害
スリップス(アザミウマ類)の被害は、見えにくいですが、深刻。
葉・花・果実などあらゆる部位に影響を及ぼし、ウイルス病の媒介者にもなるため、菜園では特に注意が必要です。
吸汁による物理的ダメージ
虫・幼虫ともに植物の表面組織を削って汁を吸います。
結果として、葉や花に銀白色のかすり傷(テラテラ光る)が現れ、花弁の色抜け、奇形、果実の変形なども起こります。




被害部位と症状
| 部位 | 症状 |
|---|---|
| 葉 | 銀白色のかすり傷、奇形、黄変、枯れ込み |
| 花 | 色抜け、奇形、開花不良 |
| 果実 | 表面の傷、変形、商品価値の低下 |
| 芽・新葉 | 成長点の萎縮、奇形、停止 |
ウイルス病の媒介


特定種(例:ミナミキイロアザミウマ)は「黄化えそ病」などのウイルスを媒介。
感染すると治療不可になるため、株の廃棄が必要になります。
他の株への感染も早いため、早期発見が重要です。
爆発的な繁殖力
メス1匹で単為生殖が可能(受精なしでも産卵)。
1匹で100〜300個の卵を産み、高温期には10日で世代交代し、放置すると1ヶ月で1万匹以上に増殖する可能性もあります。
人体への影響
スリップスが人の肌に触れると、軽いかゆみや赤みを感じることがあります。
特に汗ばんだ肌や薄着の季節に、腕や首元などに飛来して不快感を与えることも、刺されるというよりは、口器で探るような行動による刺激があります。



食べても大丈夫?
スリップスは毒を持たない害虫で、人体に有害な物質を注入することはありません。
吸汁による見た目の傷(銀白色のかすり傷や変形)はありますが、内部まで傷んでいるわけではありません。
ウイルス病(例:黄化えそ病)を媒介することはありますが、それは植物に対してのみ有害であり、人が食べても感染しません。



ただし、以下の点は注意が必要です。
| 状況 | 対応 |
|---|---|
| 葉や果実が著しく変形・腐敗している | 食べずに廃棄する |
| 表面に黒い排泄物が残っている | 洗い流してから調理 |
| ウイルス病で株全体が萎縮・変色している | 他の野菜への感染防止のため、収穫せず処分 |
スリップスの特徴は農薬を使い倒しても、いなくならないこと。
逆に農薬を使って植物は、抵抗する力を得ますが、地力免疫力がなくなり、更にスリップスを呼び寄せてしまいます。
予防が最適です。
予防と対策について確認していきます。
予防と対策
露地栽培、家庭菜園での予防や対策を説明していきます。
放置すると厄介なスリップス、予防するのが一番簡単な方法になります。
予防対策
敷きわら、刈り草の有機マルチの使用


土が見えないように敷きわらや刈り草などのマルチをしておきます。
スリップスは乾燥した地表や高温環境を好みます。
敷き藁・有機マルチは保湿・地温安定化効果があり、スリップスの繁殖環境を抑制が期待できます。
梅雨入り前の5月末~6月上旬にポリマルチをはがし稲わらに変えることで、カブリダニ類などが増加。
カブリダニが増えることで、少量のスリップスならば駆除してくれます。
白クローバーの使用


白クローバーを株間に植えることでも対策になります。
白クローバーが地表を覆うことで土壌の乾燥を防ぎ、周囲の湿度を安定化、スリップスは乾燥を好むが、湿度が高いと繁殖しづらくなります。
白クローバーの葉や茎にカブリダニなどの天敵が定着しやすく、敷き藁と同じように捕食してくれます。
防虫ネット


防虫ネット
防虫ネットをする場合は目合い0.4㎜程度のものが◎。
成虫の大きさが1㎜程度ですので、使いまわしをするにしても、1㎜以上の目なら侵入を許してしまいます。
畝の周囲にシルバーマルチを使用する


シルバーマルチ設置例
シルバーマルチは光の反射による害虫の飛来忌避。
白黒マルチは、表面が白色、裏面が黒色のマルチです。白色は、日光の光を反射し、地温の上昇を防ぎ、シルバーマルチと同様に、害虫の忌避が望めます。
白色は、夏場。黒色は冬場、地温の下がった時期が有効です。
無農薬での対策
先に紹介した予防策がかなり有効です。
スリップスは発生させないことが重要です。
発生してしまった場合は、農薬の使用も余儀なくされますが、スリップスは農薬が届きづらい花の咢(がく)などに逃げ込んでしまい、効果が期待できないことが考えられます。
また天敵を導入する方法(生物農薬)ありますが、高価な上、畑に害虫を定着させなければならず、現実的ではありません。
また、違った問題が発生しかねません。
簡単に実践でくる対策方法を紹介します。
色付きテープで誘因


スリップスは種により、好きな色があります。
甘い匂いや青色や黄色を好み、誘因される習性があります。
その習性を利用し、色付きの粘着テープを設置するのもありです。
粘着で身動きができなくなり効果的です。
寄生部位や周辺の雑草、枯れ木の処分


スリップスが寄生した葉などの規制部位はこまめに処分していきましょう。
葉が白や褐色の斑点がついている、実や葉が変形している場合は、袋に入れて密閉し圃場の外で処分しましょう。
また、周辺5m範囲の雑草や枯れ木も潜伏先になりえますので草刈りをし、処分していきましょう。
放置するとそこからまたスリップスが寄ってくる可能性があります。
お酢スプレーや木酢液は有効なのか?
酢酸が害虫の細胞膜にダメージを与えることで、アブラムシやコナジラミなどには効果があるとされています。
ただし、スリップス相手はどうでしょう?
お酢はあくまで忌避が中心で、スリップスのような繁殖力の高い害虫には十分な駆除力は期待できません。


スプレー散布


スプレー散布後の花びらの中
スプレー散布後、しばらくして花びらの中を確認しましたが、元気に活動しています。
発生後はあまり効果はありません。



予防で使うとして頻度はどのくらい?
週1〜2回程度が目安。
あまりかけ過ぎると薬害が発生するため注意が必要です。



作り方はこちらを参考にして…



木酢液はどうなの?
こちらも同様です。
忌避効果が期待できますが、除去はあまり期待ができません。
濃すぎると葉焼けや根傷みの原因になるため、500〜1000倍希釈が一般的で雨後は改めて吹き直したいですね。



予防で使うとして頻度はどのくらい?
葉面散布で週1~2回。
葉裏を中心に吹いていきます。



作り方はこちらを参考にして…



除去するとなるとやはり消毒ですか…?
農薬が第一候補にはなります。
ただ、農薬を使用しても長期戦になると思ってください。
| 系統(IRACコード) | 農薬名 | 特徴・備考 |
|---|---|---|
| 有機リン系(1B) | スミチオン ダイアジノン オルトラン | 即効性あり 抵抗性が出やすいためローテーション推奨 |
| ネオニコチノイド系(4A) | ダントツ水溶剤 モスピラン アドマイヤー | 浸透性・持続性あり 植物体全体に薬効が広がる |
| スルホキシイミン系(4C) | トランスフォーム | 新規系統 抵抗性個体にも効果が期待される |
| スピノシン系(5) | ディアナSC | 天然由来成分で幼虫に特に有効 有機栽培でも使用可 |
| アベルメクチン系(6) | アファーム乳剤 | 幼虫・成虫に有効 他の害虫にも効果あり |
| ピリジンアゾメチン誘導体(9B) | コルト | 幼虫に強い 抵抗性対策として有効 |
| メタジアミド系(30) | グレーシア乳剤 | 新規系統 長期残効性あり |
| キチン合成阻害剤 | カスケード乳剤 | 卵・幼虫に有効 天敵や訪花昆虫への影響が少ない |
抵抗性の発達を防ぐため、異なる系統の薬剤を交互に使用し、即効性のものと持続性があるものを組み合わせてしようしていきます。



スリップスについては発生させないような努力が大事ですね。
最終手段が有機で対応が難しくなります…( ゚Д゚)
基本的なことになりますが連作になるようなことはしない。
雑草はこまめに処分が予防の近道になります。
スリップス(アザミウマ) 無農薬での対策
今回は、小さい悪魔、スリップスについて解説しました。
バラ栽培をしていると、発生すると除去しきることができず、農薬散布→吸汁した花をカットし処分を繰り返してようやく正常化していきます。
取りつかれるとかなりのリスクを背負うことになるため、予防に力をいれて頂きたい害虫です。
参考にしてください。
今回、以上。
最後までお付き合い頂きありがとうございました。
その他、害虫対策についてはこちら…



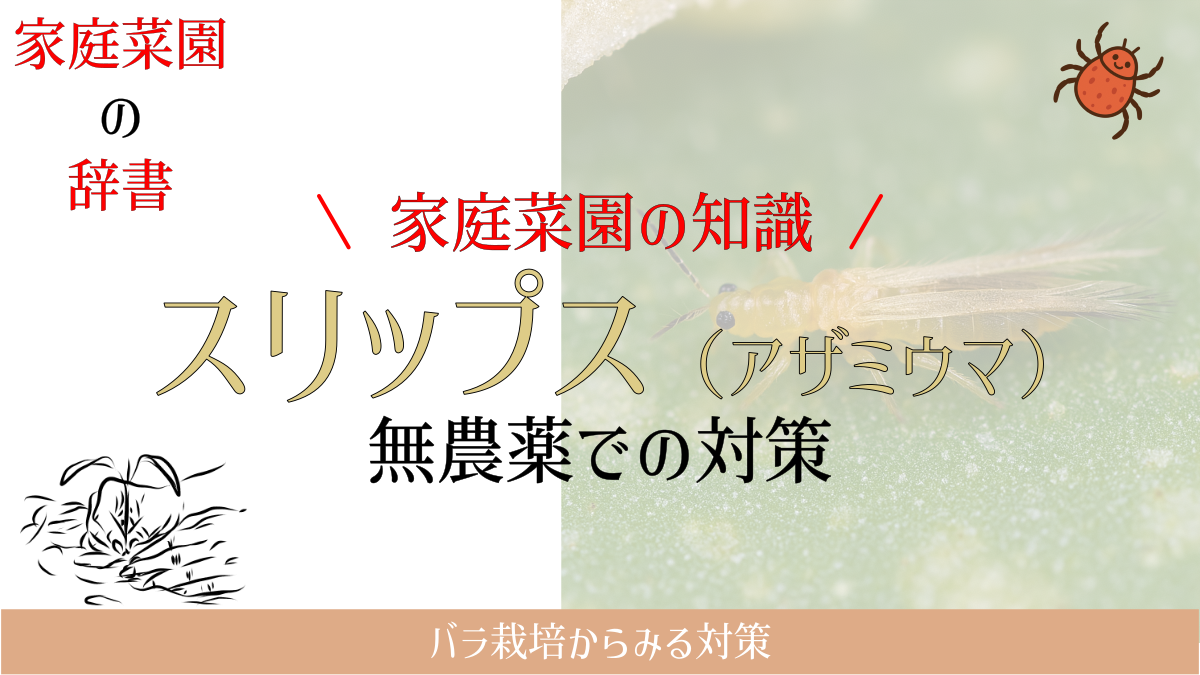



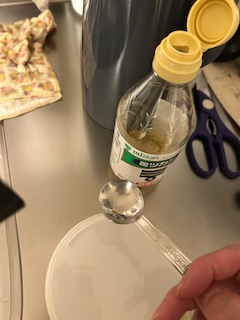


コメント