
今回は「菌ちゃん農法」で必要な有機物の調達についてお話しします。
『糸状菌のエサを調達する。』
糸状菌は炭素分の多い有機物を好みます。
炭素分の多い有機物は、畑や山で調達できるものがほとんどです。
今回は畑に入れるために必要な有機物について説明と調達について、これから農法を試してみる筆者が紹介します。
- 菌ちゃん農法で畑に入れる有機物
- 保管方法について
糸状菌の好む環境づくり



まず、畑の土を糸状菌の好む環境にしていきます。
前回、糸状菌の働きで野菜を作るプロセスについて説明しました。
まず、畑の土に糸状菌や良い増やさなければなりません。
そのために、糸状菌のエサとなる有機物を準備していきます。
準備する有機物 – 1
糸状菌は炭素分の多い有機物が必要です。
炭素分の多い有機物は、窒素分の多い有機物より、外に放置しても腐敗しづらく、分解に時間がかかります。
窒素分が多いと、発酵は早いが、糸状菌は増えづらく、発酵促進剤の米ぬかは使用しない。
また、好気性で酸素を好む菌のため、空気が豊富な場所でよく増えます。
以下で紹介する有機物の中で調達しやすいものを集めていきます。



草刈りや落ち葉拾いを常時しています。
私はそれらを使って土づくりをしていきます。
刈草
必要量:5㎏/㎡ (乾燥時)


刈ったばかりの雑草


野ざらしにした雑草
葉がツンツンしていて茎が固い雑草が炭素を多く含んでいます。
やわらかい雑草は窒素分が多く、潰れて空気を保ちづらいため、極力選んで使った方が良い。
発酵させるため、畑の片隅に写真のように野ざらしにして、数ヶ月程度そのままにしておきます。
使用時は、雨降り後、水で湿らせたものを使用します。
おすすめの雑草


スズメノカタビラ


エノコログサ


オヒシバ


メヒシバ


セイタカアワダチソウ


ススキ
畑の脇や無耕作の畑に生える雑草が殆どです。
柔らかい草より固い雑草の方が土づくりに最適となります。



私は、草刈りの過程で分別はせずに山積みしました。
畑周りの草を刈って畑の隅に保管しています。
落ち葉
必要量:5㎏/㎡ (乾燥時)


落ち葉


糸状菌のついた葉
落ち葉の中でも、スギの葉は、小さな葉の間に空間があるため、糸状菌がつきやすい。
採集の際に枝葉が混じりますが、構わず集めていきます。
数ヶ月程、野ざらしにしたものを使用していきます。
もみ殻
必要量:70~80ℓ/㎡


もみ殻もおすすめです。
もみ殻は、畑の土の通気性を上げる為に使用されますが、菌ちゃん農法の場合は、新鮮なもみ殻は使用しません。
新鮮なもみ殻は水をはじくため、6ヶ月程、野ざらしにしたものを使用します。
使用する際は、十分に湿っていて、表面に糸状菌のついたものがあれば優先的に使用します。
竹(タケ)
必要量:40ℓ/㎡


竹 チップ状


糸状菌のついた竹
竹は糸状菌がよく増え、鉄などの微量要素を含んでいて畑への栄養供給の面でもプラス。
チップ状にすると乳酸菌が優先的に増えてしまうため、使用ができなくなります。
数ヶ月、野ざらしにして、1~10㎝程度の長さにして使用していきます。
木
必要量:45ℓ/㎡


長さ3~5㎝程のチップ状になったものを使用します。
樹皮は特にミネラルが多い。
数ヶ月、野ざらしにしたものを使用していきます。
白い菌糸がついたものを使用していきます。



繊維のくずも投入すると糸状菌が増えるようです。
色々なものを試しながらやっていきたいですね。
繊維は化学繊維は使用しないため、結構ハードル高めです。
向かない有機物
上記の3点はチッソ分が多く、土に入れると乳酸菌や酵母菌などが増殖しやすく、糸状菌が増えづらくなります。
また、腐敗に傾くため、一時的には土を肥沃になりますが、毎回の作付け毎に投入の必要があります。
完熟堆肥と比べて
完熟堆肥を施すのが一般的ですが、土の団粒化をするのに時間が掛かることと、菌ちゃんを育てるために、草や落ち葉を使っていきます。
菌ちゃん農法における完熟堆肥のデメリットは以下の通りです。
- 畑の土の中で発酵をさせないため、堆肥置場を設けて外で発酵を促進させる
- 発酵過程で養分(チッソ)は熱とガスとして失われる
- 無機化がすすみ、生の有機物を施すときに比べ、生物性が乏しくなる
発酵型の畑を作るスピードは、上記の有機物を投入した場合の方が、完熟堆肥を施すよりも早くなります。
糸状菌が増え始めればどんどん進んでいく。
発酵型になれば、病気や連作障害が減っていくメリットがあります。
菌ちゃん農法 雑草を集める まとめ
今回は、畑に投入する雑草を始めとした畑に入れる有機物について紹介しました。
畝をつくるまでにまず、有機物を集めて野ざらしにして発酵させる必要があります。
今回は、雑草や落ち葉の㎡あたりの必要量を含めて、紹介しました。
私の場合は、山間部にある家となりますので、落ち葉の調達が一番容易になります。
落ち葉と雑草をベースに畝を作っていく予定でいます。
今回は以上です。
最後までお付き合い頂きありがとうございました。
菌ちゃん農法を知りたい方はこちら…
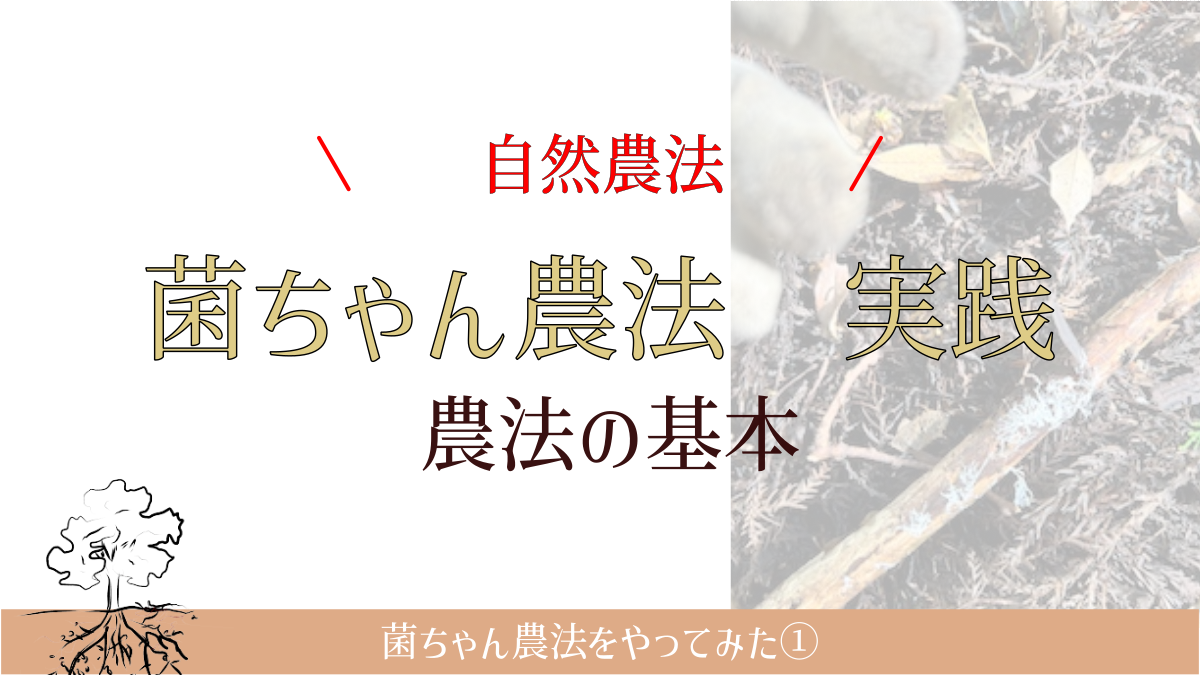
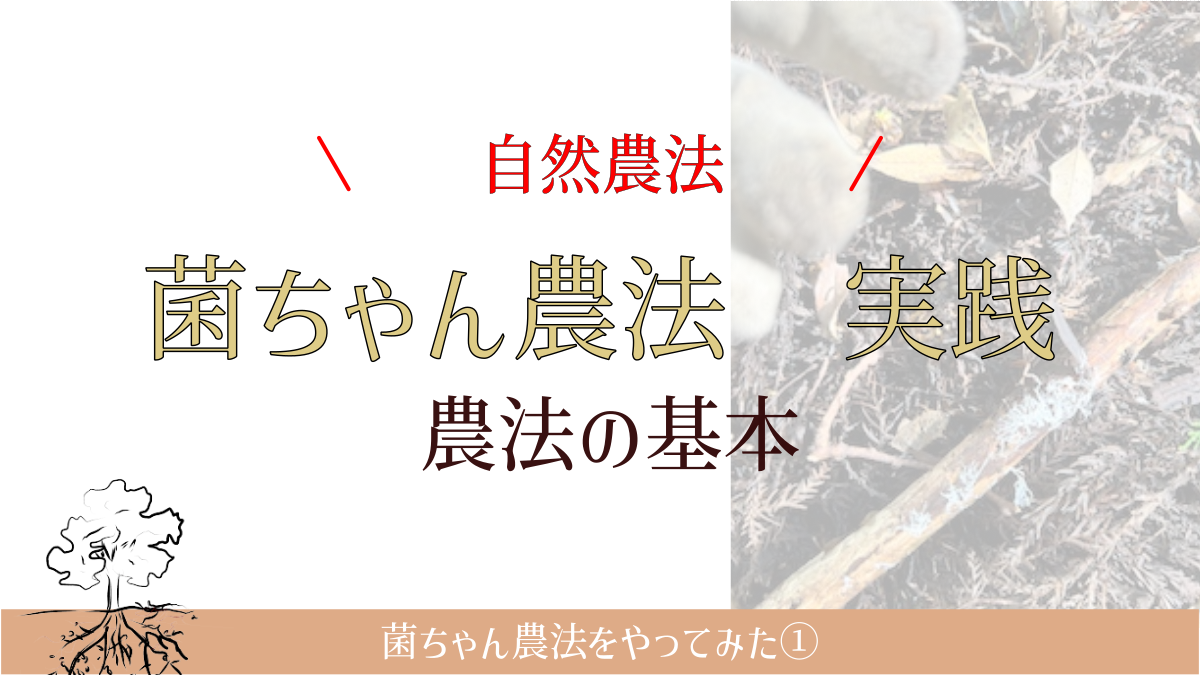
菌ちゃん農法のスケジュール感覚を把握したい方はこちら…
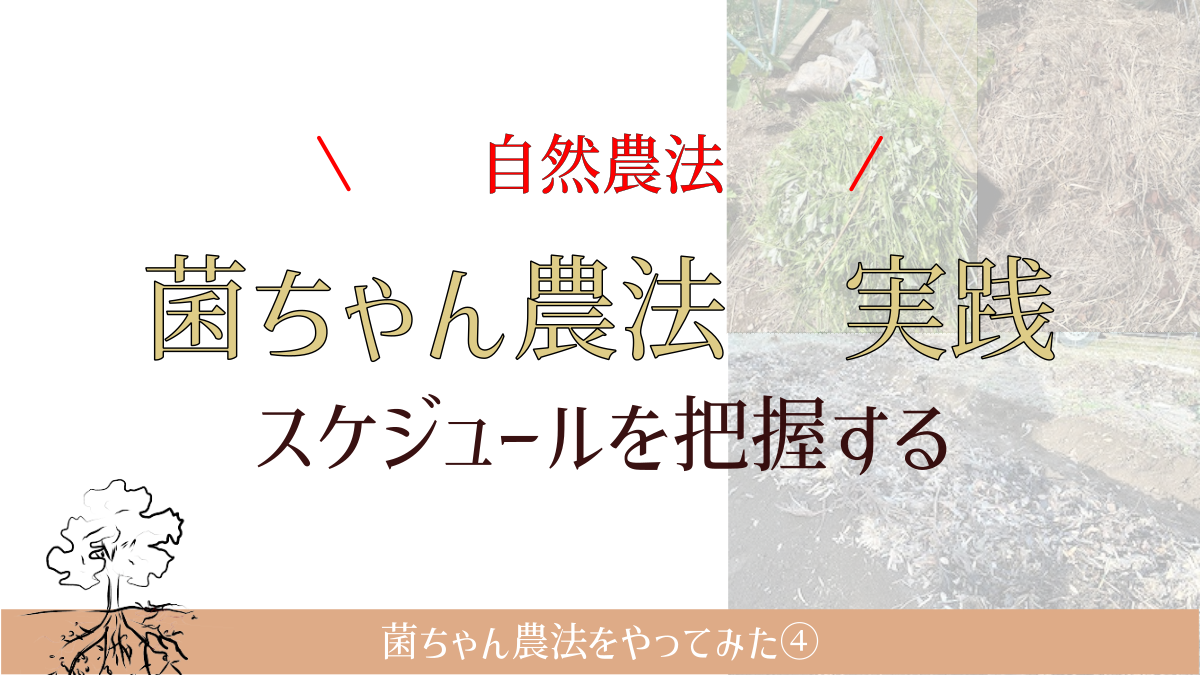
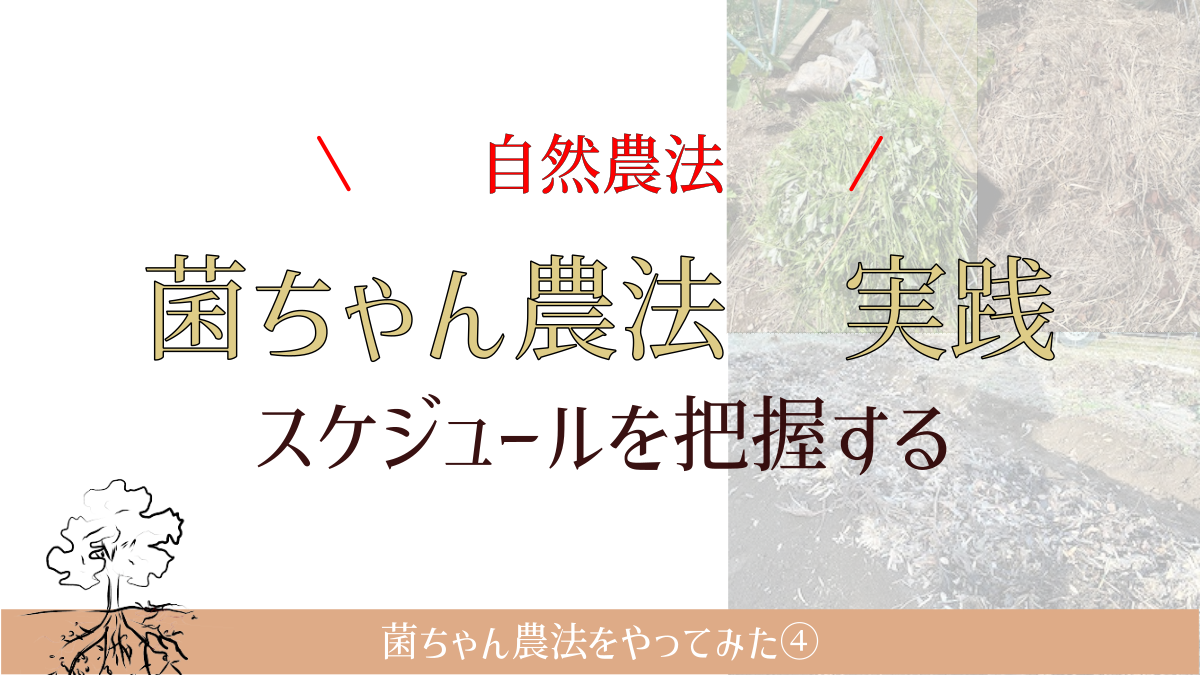
菌ちゃん農法がわかる吉田俊道先生の本はこちら…

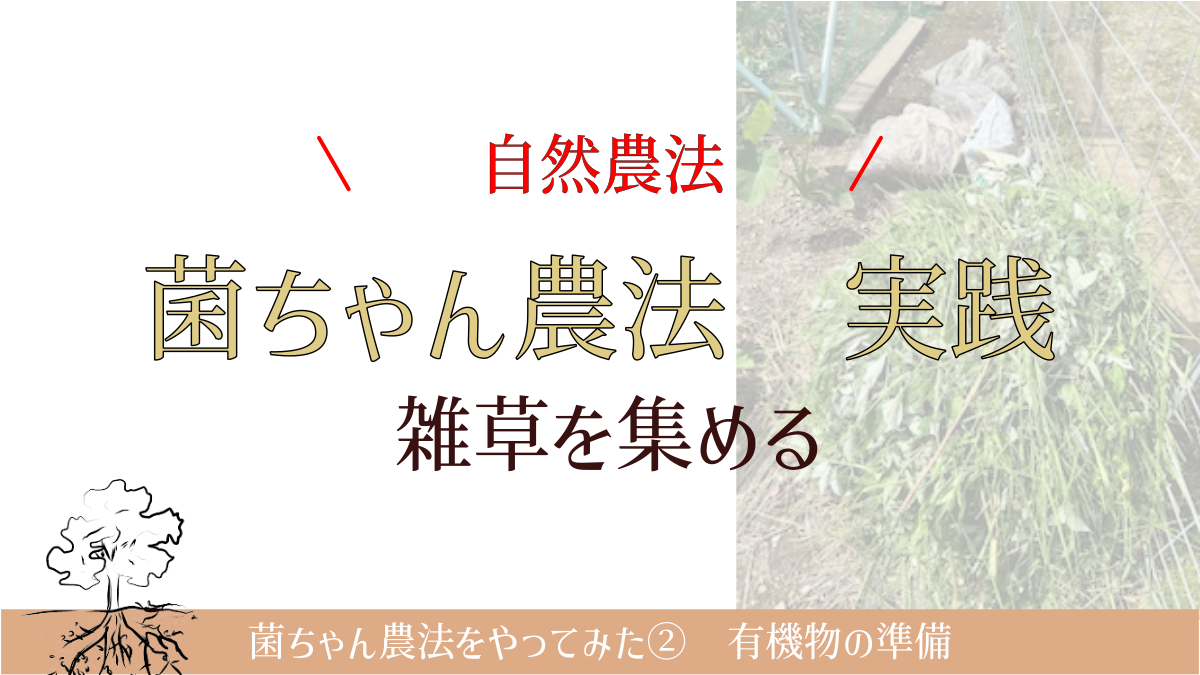




コメント
コメント一覧 (2件)
大変勉強になりました、自分の作業の参考に致します。
コメントありがとうございます。
畝も11月に作成予定です。
続編も時間を見つけてアップしていきます。
また、よろしくお願いします。