
畑で野菜をつくる前準備について一度整理してほしい。



道具の選び方から土づくりまで一通り記事にしましたが、わかりづらいですよね。
「家の庭や畑で家庭菜園したいが準備の流れが知りたい」
こんな悩みはありませんか?
家庭菜園を始めたいと思ったら
- 道具を揃える
- 畑を調達する
- 野菜を作る畑の準備と計画をする
をしていきます。
農家をしながら、家庭菜園を楽しむ野菜まみれの人生を送る筆者が、流れをまとめました。
この記事を読んで頂ければ、野菜をつくる前段階の流れがわかるようになります。
家庭菜園を始める前に読みたい必須の一記事!
- 家庭菜園で野菜をつくる前準備の流れ
畑で野菜をつくる準備をする



畑となる場所、畑が確保できたら早速、準備をしていきましょう。
ここでは野菜を植え付けるまでの流れを説明していきます。
作付け計画から野菜を植え付けるまでの流れ
畑となる場所でどんな野菜が作りたいのか、整理をしましょう。
野菜を作る上で注意したい「連作障害」。
野菜を作る上で、スケジュールと植える場所、相性などを整理していきましょう。
野菜によって、注意点は変わります。
計画を作るにあたり注意点を整理してみましょう。
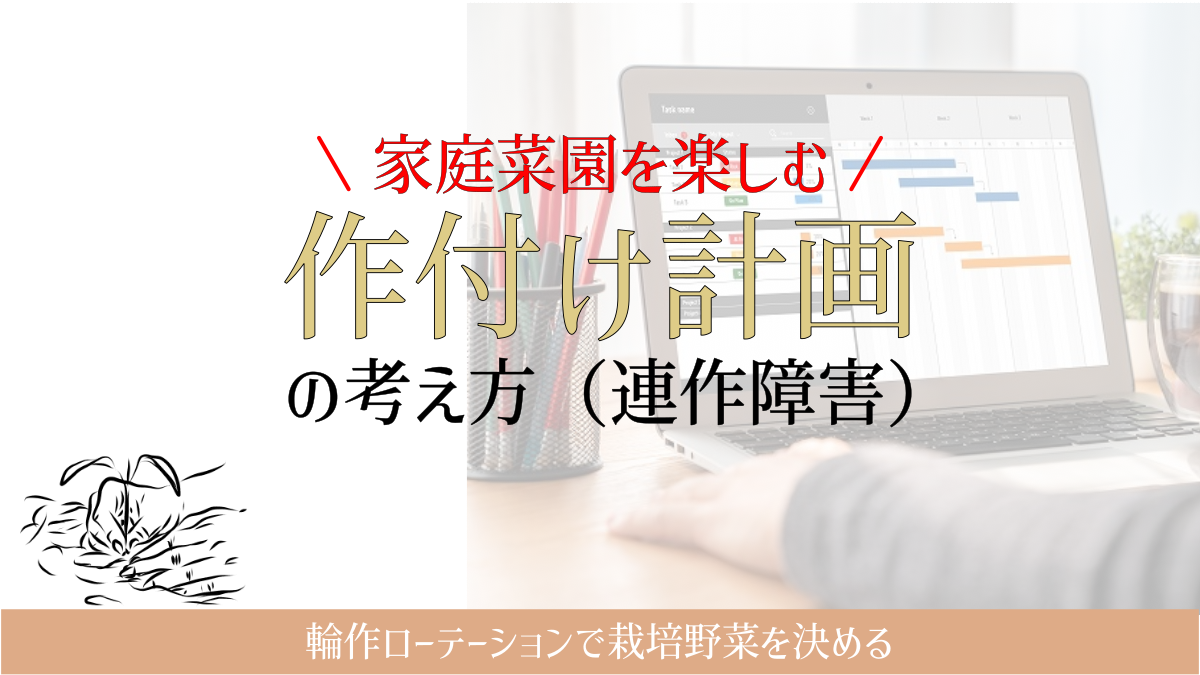
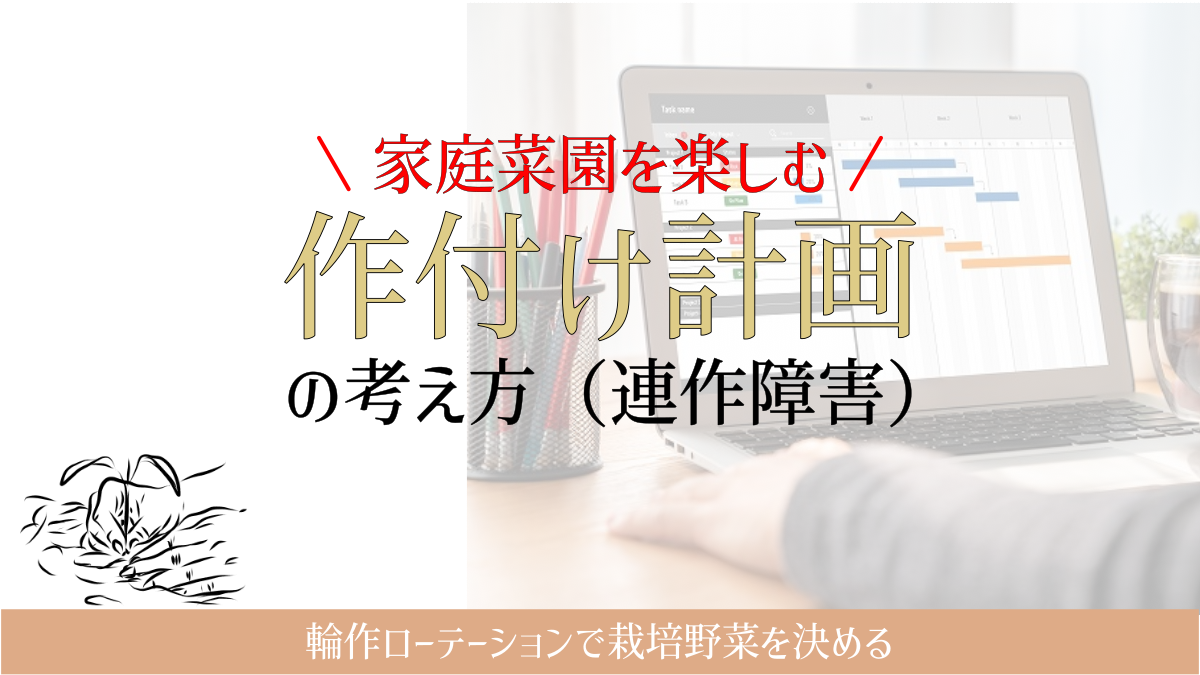
作付け計画は大事です。
余裕があれば、自分なりの計画書を作っていきましょう。



長く野菜をつくるためのり基本的な注意となります。
目を通してみて。
畑がある方
畑が既にあり、これから野菜を作っていきたい方はこちらを参考にしてください。
野菜を作る前にすることは、野菜を作る土づくりを行います。
良い土は、ふかふかで肥料の吸収がよく、みみずや微生物の動きが活発な土となります。
そのために、微生物が安心して生活できるように、エサである堆肥を投入していきます。
畑を作って家庭菜園を楽しみたい方
庭に畑を作って家庭菜園を楽しみたい方はこちらを参考にしていください。
畑を作る計画をし、自分が育てたい野菜が育てられる環境か調査していきます。
日当りや風通しなどを確認し、石や草を整理しブロックなどで見切りをし、畑を作っていきます。
土壌の確認をし、土壌質により堆肥と改良用土をまぜて野菜の土づくりを行っていきます。



堆肥投入は植付から逆算して3週間前に行います。
これは双方の方、共通です。
堆肥を入れて、生物性改善、微生物の動きを活発にしました。
次は、育てる野菜にあった土の酸性度にしていきます。
このpHを調整することで、肥料の利きを良くしていく為です。
畑に限らず、雨がよく降る日本では、何もしなければ酸性の土に傾き、野菜を育てる土壌ではなくなってしまいます。
野菜のpHを調べ、自分の畑の酸性度(pH)を調べ、調整していきます。
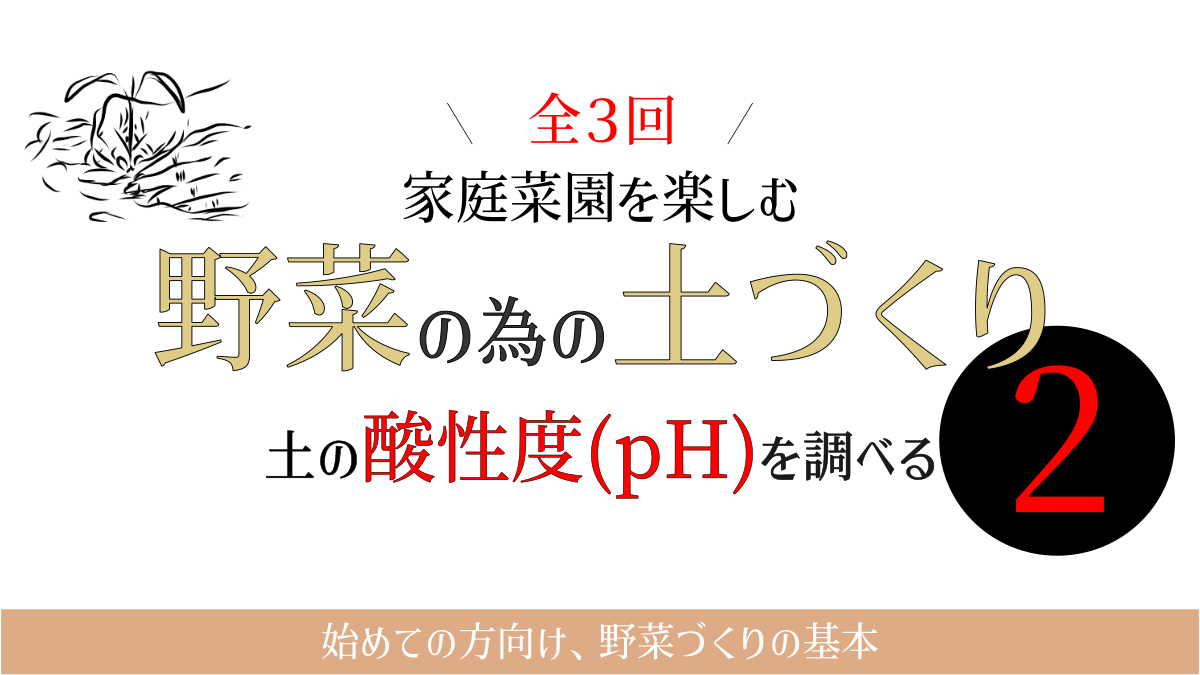
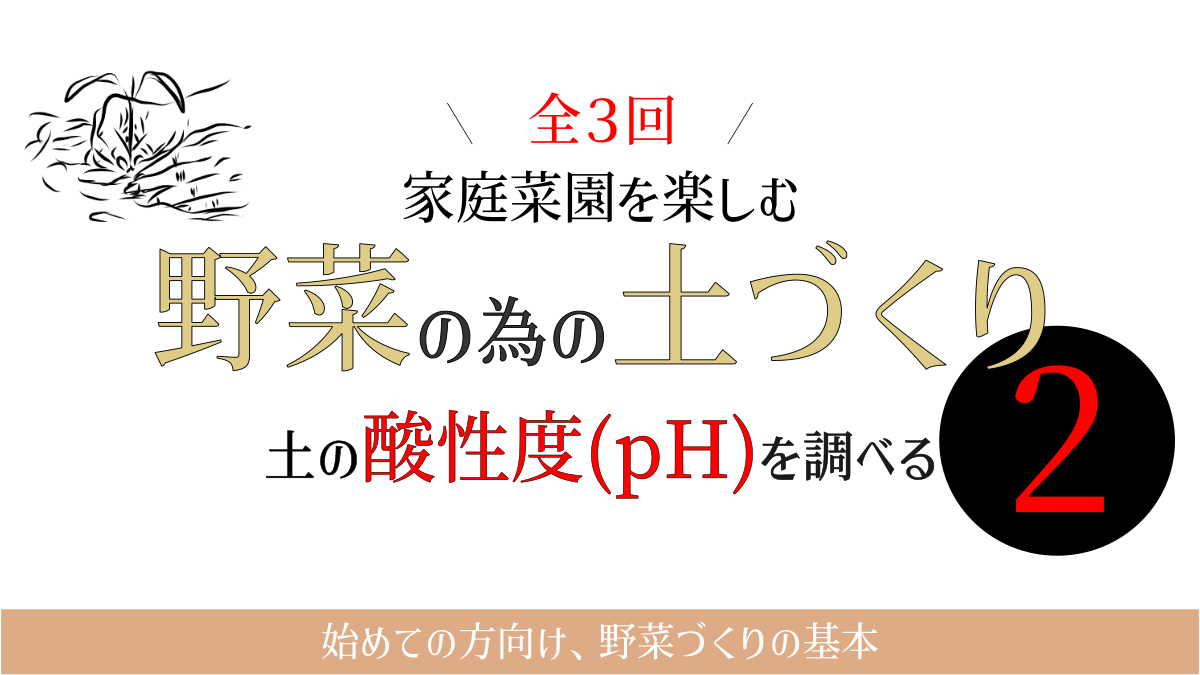



pHは必ず確認しましょう。
調整に使う石灰は一部の肥料と混ぜると良くない為、焦らずじっくり取り組んで‼
育てたい野菜の生長を補助するため、肥料をセットしていきます。
植付時におこなう肥料のことを元肥(もとひ・もとごえ)と呼びます。
pH調整を行った後に肥料を投入することで、肥料の効果をあげていきます。
野菜を収穫すれば、野菜と一緒に土に蓄えられた栄養が無くなります。
その栄養を補填するのが肥料の役割です。



肥料が皆さん一番困ることだと思います。
私なりの方法を紹介してます。
参考にしてください。
畝(うね)づくりは元肥と同時に行っていきます。
畝を作る上で作業性を良くし、野菜の管理をしやすくする。
野菜づくりに畝は不可欠です。
畝のように栽培床を高くすることで、根を張れる、地温が上がる、水はけ、通気性がよくなるなどメリットが発生します。



散歩していると、畝をきれいに作っている畑に見惚れます。
畝をピシッと作る人って憧れます。
元肥を施し畝を作った1週間後に種まき、苗の植え付けをしていきます。
野菜にあった植付方法を選択していきます。
種まきには、筋まき、点まき、ばらまきがあります。
トマトやナスなどの野菜は種はポットに植付し成長した苗を畑に植え付けしていきます。





苗を植えるまでの基本的な流れは以上となります。
おいしい野菜を作る上で、楽しみながら準備をしていきたいですね。
家庭菜園で使う肥料や用土



化学肥料、有機質肥料、用土についての詳細はこちらを参考にしてね。
家庭菜園で使用するであろう、米ぬかなどの有機肥料、単肥や化成肥料などの化学肥料。
土壌の改良などに使用する用土や堆肥についてリスト化し、特徴をまとめています。
野菜作り 畑の準備の流れ まとめ
畑で野菜を育てる前段階について投稿させて頂いた記事のまとめとした記事をアップさせて頂きました。
流れで見て頂ければ、少しはお解り頂けたでしょうか?
おいしい野菜を作る上で育てている過程より、土をつくる作業が重要であると個人的に考えています。
今年はこの方法で元肥をした、来年は違う方法を試してどんどん良くなっていきます。
ひとつの基準として当記事を参考にして頂ければ幸いです。
今回は以上となります。
最後までお付き合い頂きありがとうございました。
自然農法に興味がある方はこちらも読んでみて…
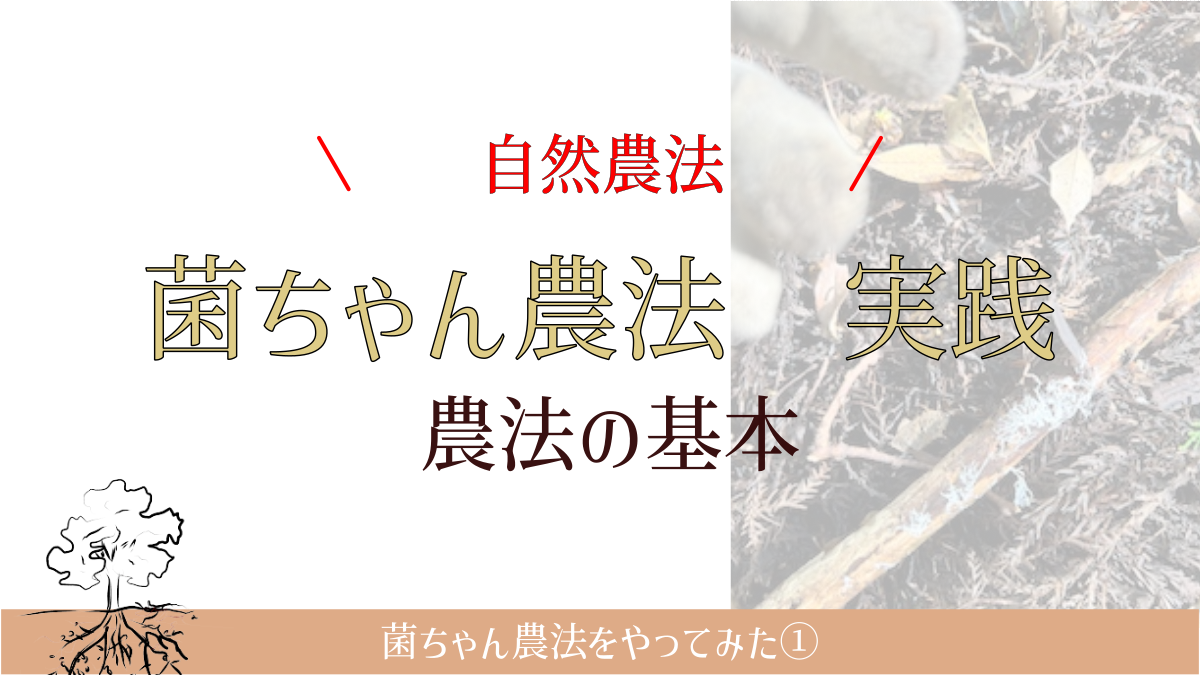
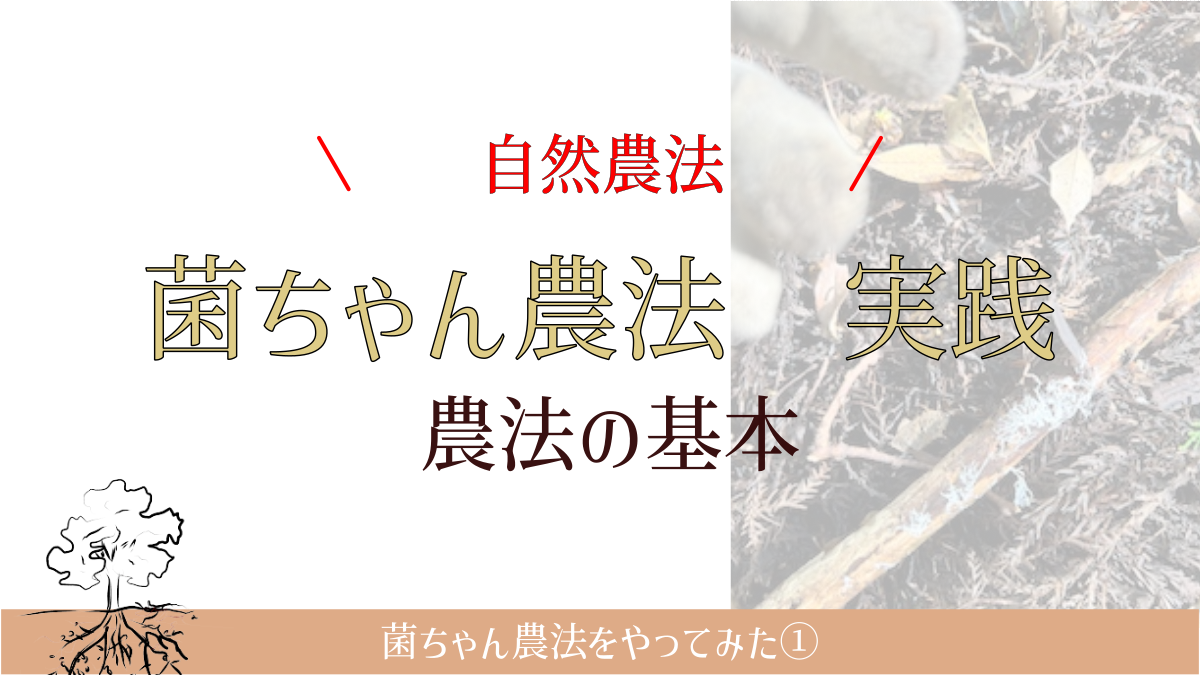


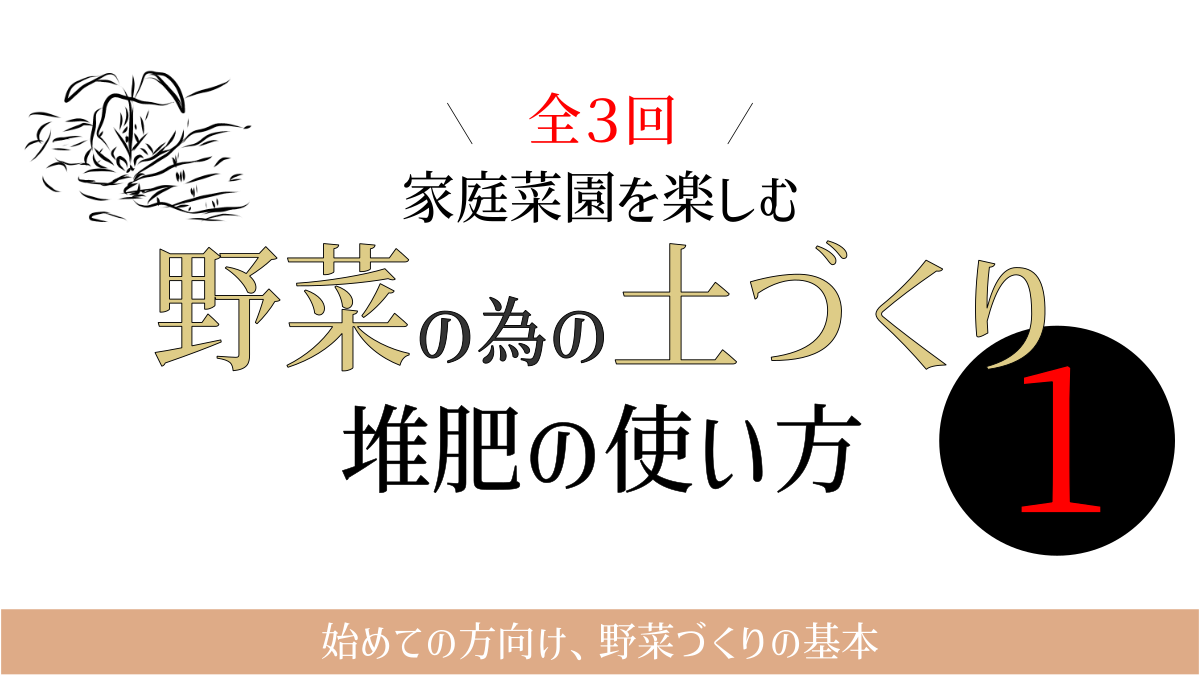

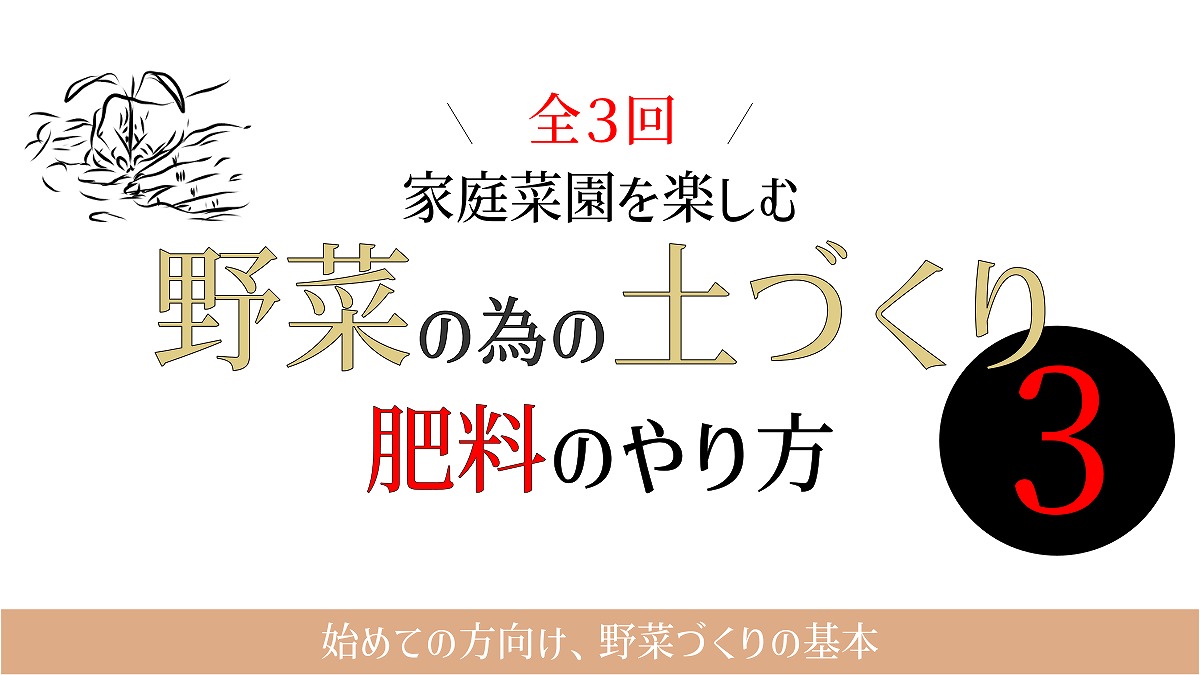
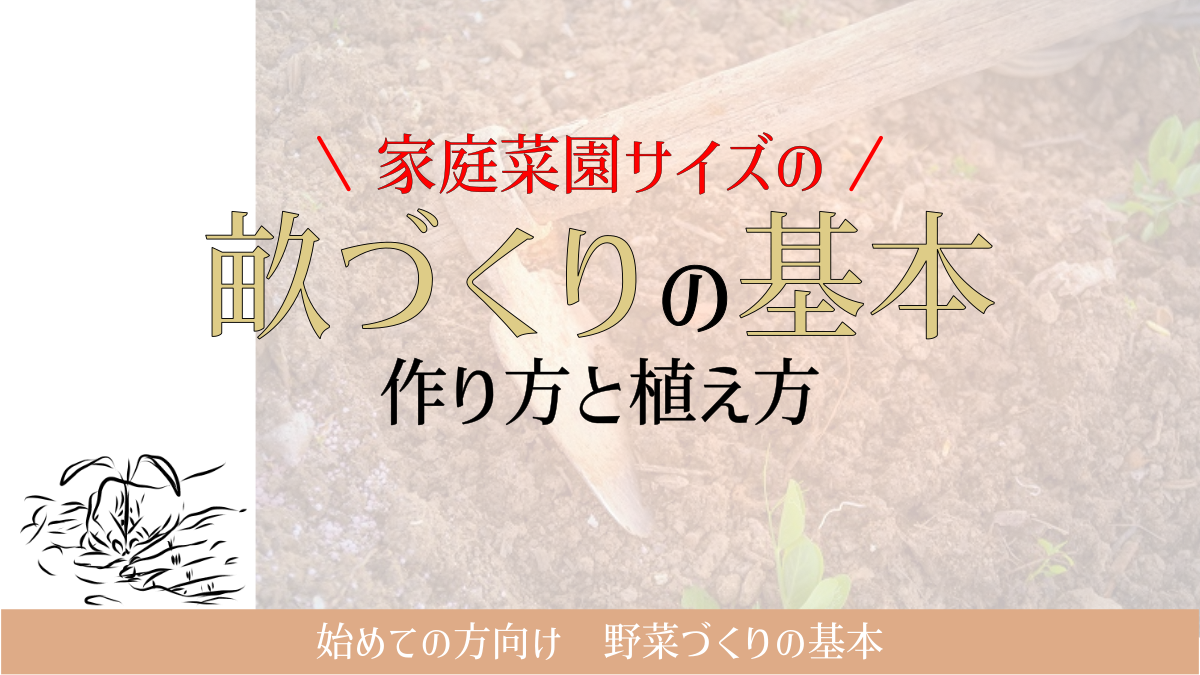
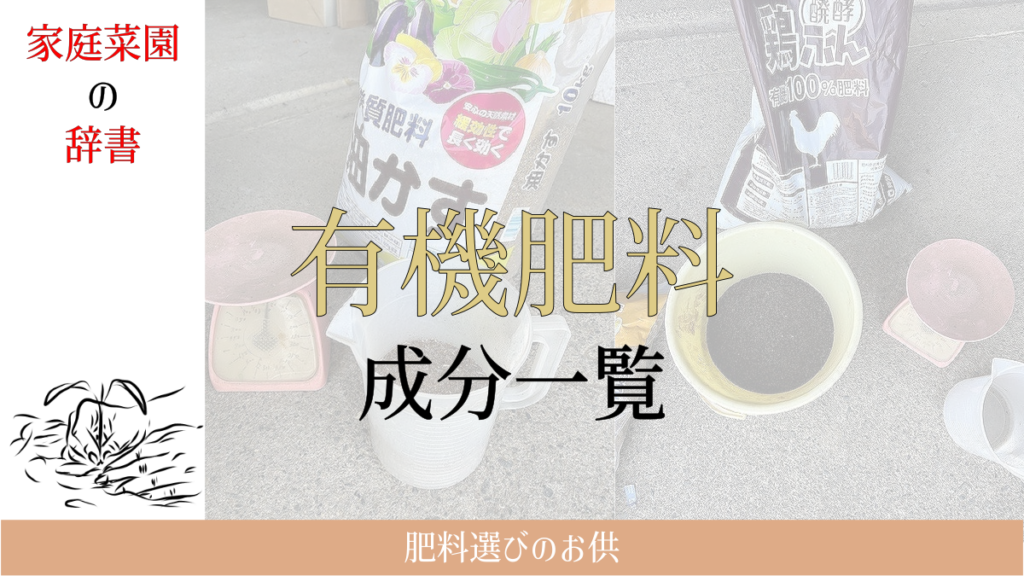

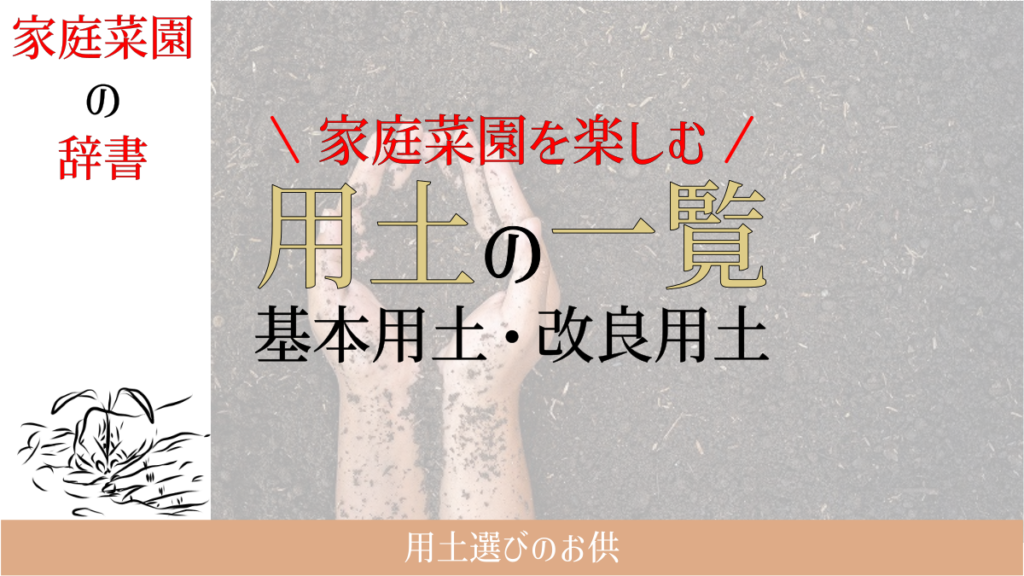
コメント